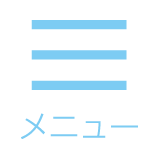よくわかる!こどもの歯みがき②
2022年10月12日
☆混合歯列期(乳歯と永久歯が混ざり合う時期)
乳歯が抜け、新しい永久歯が出てくるので、歯並びが一時的に不揃いになります。日々歯の生え方が変化するので、よく確認して丁寧に歯みがきしましょう。
6歳臼歯というのをご存知でしょうか?
前歯のように抜けてから生えるのではなく、6歳前後に一番奥の乳歯のさらに奥から出てきます。気がつかないことが多いのですがとても大切な永久歯です。特に6歳臼歯は今までの乳歯と違い、噛む面の溝が深いので虫歯になりやすい傾向があります。6歳ごろになったら奥歯も気をつけてみていきましょう。
永久歯が生えかけのときは、歯ぐきを傷つけないように、やわらかいワンタフトブラシでやさしく磨きます。しっかり生えてからは普通のかたさの歯ブラシにしましょう。
自分で進んで歯みがきをするために、好きなキャラクターの歯ブラシやコップでモチベーションを上げたり、短い歯みがきにならないようタイマーを使うのもおススメです。